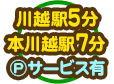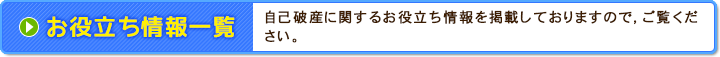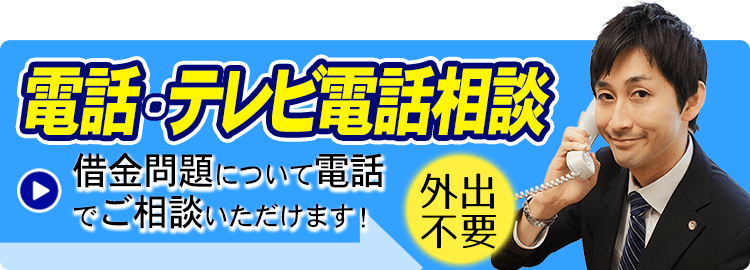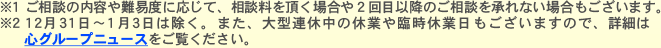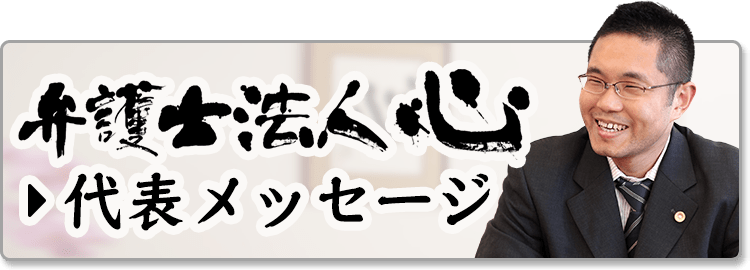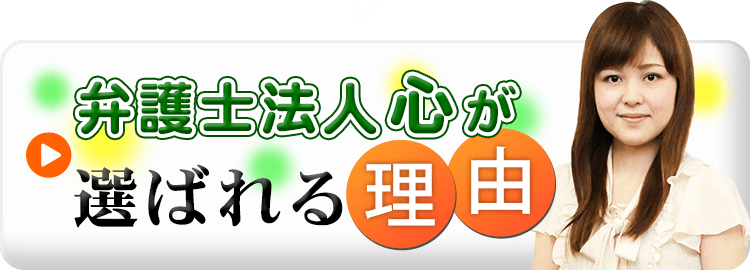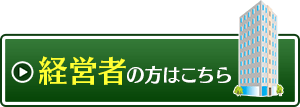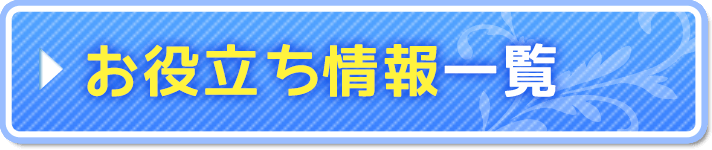Q&A
自己破産で同時廃止となるケース|同時廃止の流れ・期間・費用は?
借金が膨らんで返せない状態になったとき、裁判所での手続を通じて債務の返済義務を免れる債務整理手段が「自己破産」です。
この自己破産には「管財事件」と「同時廃止事件」という二つの手続きの方法があります。
これは、債務者の事情(借金をした理由・金額や、所有する資産額など)を鑑みて、裁判所が決定します。
管財事件は、同時廃止よりも手続きが煩雑で時間もかかります。
よって、債務者としては、できる限り同時廃止により借金問題を解決したいところです。
今回は、自己破産が同時廃止事件となる条件と、同時廃止事件の流れ・期間・費用などについて解説します。
1 「管財事件」と「同時廃止事件」とは何か
先述のとおり、自己破産には「管財事件」と「同時廃止」という2種類の手続きがあります。
端的に言うと、同時廃止の方が比較的単純な手続きで、時間もお金も管財事件ほどかかりません。
同時廃止のデメリットや問題点は、ほぼないと考えて良いでしょう。
もっとも、同時廃止を希望したとしても、必ずしも同時廃止事件になるというわけではありません。
自身の保有する財産の価値や、債務を作ってしまった理由等によって、裁判所の判断でどちらになるかが決まるのです。
⑴ 管財事件
まず、破産手続きの原則形態である、管財事件となるケースを説明します。
(逆に言えば、管財事件となる条件を満たさなければ同時廃止事件として処理されますが、破産法上は管財事件が原則で、同時廃止は例外としての位置づけです。)
まず、基本的に一定の評価額以上の財産があると、「管財事件」になります。
自己破産は借金などの債務の返済義務をすべて免除する代わりに、債務者の財産を処分・換価し、債権者に配当します。
この配当に値する財産(例えば、高価な車やマイホーム、33万円を超える現金など)があれば、一般的には管財事件になります。
また、債務を作ってしまった理由によっても管財事件となり得ます。
具体的な例としては、次のものが挙げられます。
- ・カード現金化(クレジットカードの枠を現金化すること)
- ・換金行為(カード払いで購入したものを売却するなど
- ・賭博(パチンコ、競馬、競艇などのギャンブル)
- ・浪費(不必要なものや高価なものを大量に購入するなど)
- ・射幸行為(株取引など)
上記のような事情は「免責不許可事由」に該当し、管財事件として破産管財人が経緯等を詳しく調査をする必要が出てくるのです。
(※悪質な免責不許可事由があると最悪の場合免責が認められませんが、手続きに積極的に協力したり、反省文を作成し裁判所に提出したりする等、再度同じことをしないとことを示せれば、自己破産が認められることもありますのでご安心ください。)
管財事件になると、破産手続開始決定時に裁判所が「破産管財人」を任命します。
破産管財人は債務者の財産を管理したり、免責不許可事由の調査を行ったりするのですが、この破産管財人の報酬は債務者負担となるため、その分費用も多くかかってしまうのです。
⑵ 同時廃止
裁判所が定める基準以下の財産しか保有しておらず、免責不許可事由もない場合、破産管財人が行う業務もないため、基本的には簡易的な手続きである同時廃止となります。
実務上、自己破産を行う方は、目立った財産を所有していないことも多いです。
マイホームやマイカーを持っておらず、(各裁判所の基準にもよりますが、概ね、)33万円以下の現金・20万円以下の預貯金しか財産がないという場合には、同時廃止が選択される可能性が高くなります。
- 【2回目の自己破産は同時廃止が難しい】
-
法律的には、前回の免責確定から7年を経過していなくとも、2回目の破産の申立ては可能です。
しかし、7年を経過していない場合は免責不許可事由とされており、また、7年を経過していたとしても2回目の申立ての際は、債務の形成理由に関する審査が厳しくなります。
一度自己破産しているのにもかかわらず、再度借金を重ねて自己破産しようとしているので、「今回免責を許可してしまうと、今後も借金と破産を繰り返すかもしれない」と思われてしまうからです。
そのため、財産をほとんど持っていなくても、「免責調査」のために管財事件になる可能性は高くなります。
2 同時廃止手続きの流れ
自己破産は、厳密に言うと「破産手続」と「免責手続」の二つの手続きを経て終了します。
破産手続は「破産者の財産を換価して債権者に配当する」手続で、免責手続は「裁判所から免責許可を得る」ための手続です。
⑴ 破産手続開始決定・破産手続
先述のとおり、同時廃止の場合は債権者に配当すべき破産者の財産はありません。
配当するほどの財産がなければ、破産手続開始決定と「同時」に破産手続を「廃止(終了)」する決定が出ます。
これが「同時廃止」です。
つまり、同時廃止のとき、「破産手続」は実質行われません。
管財事件のときは、破産手続開始決定がなされると、選任された破産管財人が財産を換金(換価)して債権者への配当を行います。
換金・配当する財産がないとしても、配当に至る財産がないという確認作業を経る必要があります。
⑵ 免責手続(免責審尋、免責許可)
同時廃止ならば、自己破産申立てから2~3か月後に、裁判所が「免責許可決定」をすることが多いです(裁判所によっては、免責許可決定に先立って「免責審尋」と呼ばれる申立人と裁判官との面接が行われる場合もあります)。
免責許可決定から約1か月後、免責許可が確定します。
免責許可が確定すれば、債務者の債務の返済義務はなくなります。
管財事件の場合は、免責許可決定の前に「免責不許可事由」に関する調査を行う必要があるため、ここでも同時廃止より時間がかかります。
同時廃止の期間ですが、弁護士の着手から早ければ3~4か月ほどで免責を得られるでしょう。
申立準備(書類収集・作成)に1か月ほど、申立てから2~3か月で免責審尋、その後1か月で確定するという流れです。
3 同時廃止のために必要な費用
同時廃止事件は管財事件に比べてコストは低いですが、次の費用が必要です。
裁判所への予納金:10,000円~13,000円(裁判所によって異なる)
予納郵券代:数千円(債権者の数・裁判所によって異なる)
弁護士費用:20〜30万円(状況によって異なる)
裁判所への予納金や予納郵券代は、管財事件の場合も変わりません。
しかし、管財事件の場合は、これまで述べたとおり破産管財人の費用が別途かかり、これは最低でも20万円ほどです。
また、管財事件は複雑な手続きで、裁判所へ赴く機会などもあるため、出廷費なども含め弁護士費用の相場も30〜50万円に上がります。
4 自己破産は弁護士へ相談を
自己破産を申し立てるには、多くの書類の準備が必要です。
管財事件でも同時廃止でもそれは変わりません。
自己破産を検討しているなら、できるだけ早めに弁護士に相談し、サポートを受けることをお勧めします。
「自分の場合は同時廃止になるか」という見通しについても、弁護士にご相談ください。
弁護士は申立書類の準備のみならず、状況に応じた適切な判断をすることができます。
債務者の方の置かれている状況によっては、自己破産以外の債務整理方法でも借金問題の解決が可能であることもあります。
借金問題は相談しにくいもしれませんが、時間が経過すると悪化することが多いため、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
自己破産を始めとした債務整理の解決実績豊富な弁護士が、適切な解決方法をアドバイスいたします。
管財人とはどういう立場の人ですか? 自己破産における破産者の復権とは?